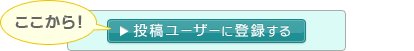観光スポット|
神社・寺院
投稿ユーザー様からの口コミ投稿
押立神社 の投稿口コミ一覧
1~5件を表示 / 全5件

押立(おしたて)神社は、火産霊(ほむすび)神と伊邪那美(いざなみ)神を祭神とし、奈良時代後期と言われる開基当初は、この地から6km程東の押立山頂にありましたが、その後、平安時代の天元元年(978年)に、この地へ移転したと言われています。17の村からなる押立郷(庄)の総社として、古来「大宮さん」と呼び親しまれ、多くの信仰を集めてきました。 押立神社大門は南北朝時代の延文2年(1357年)建造、入母屋造檜皮(ひわだ)葺の四脚門で国指定重要文化財です。押立神社本殿は同じく南北朝時代の応安6年(1373年)建造、三間社流(ながれ)造檜皮葺で、こちらも国指定重要文化財です。通常、本殿は拝殿よりも高い位置に造営されますが、押立神社の本殿は拝殿と同じ高さにあり、珍しいと言われています。 現在は宝物館に収蔵されていますが、木彫りの猿像が本殿前に置かれていました。これは押立山から神様を迎えた際に、神馬に随行して無事に送り届けたのが猿だったためと考えられています。現在、本殿前には木彫り猿像の代わりに石造りの猿像が置かれています。 また、押立神社には、60年に一度の「ドケ祭り」という奇祭が伝わっています。鬼面を着けた踊り手が、「ドッケノ、ドッケノ、シッケノケ」と囃し立てながら行進するもので、「ドケ」は「道化」から発したものとも言われ、あるいは、押立山から神様をお迎えした時のお渡りの様子を再現したもので、「神様がお通りだ、退(ど)け退(ど)け」という意味とも言われています。大変珍しい祭りのため、東近江市指定無形民俗文化財となっています。 ただ、60年に一度という頻度の少ない祭りでは、次世代への伝承が難しいため、保存会が作られており、還暦を祝う節分祭でドケ祭りが奉納される等、踊りの伝承活動が行われています。ドケ祭りの伝承という目的に向かって、地域の結束が図られているのが見て取れます。 前回のドケ祭りは昭和46年(1971年)でしたので、次回は令和13年(2031年)に開催されます。健康に留意して、私も見届けたいと思います。
旧滋賀県愛知郡湖東町であったエリアで、東近江市に鎮座する自然に溢れた歴史ある神社です。地域の貴重な森林として、環境保護指定を受けた社叢林の中に神社はあります。 二基の大鳥居に挟まれたところに広い駐車場がありますので、車両での参拝者には大変便利です。参道入口にある木製の大きな看板が目印となります。 一直線の参道を進むと、左手に瓦屋根の手舎水と井戸があり、そして大門があります。大門をくぐると荘厳な雰囲気の本殿がございます。本殿、大門とも国の重要文化財に指定されております。 向かって本殿右横奥にある白い建物の校倉造の構造、大門横にある宝物館、60年に1度行われる『ドケ祭』のお話など、社務所の方が丁寧に説明していただきました。 ちなみに、宝物館内には『ドケ祭』で使用される神輿や神楽などが収蔵されているとのことです。 毎年節分には、境内で豆まきが行われます。また、ドケ祭保存会の方々による『ドケ踊り』も奉納され、毎年大変な人出で賑わうのだそうです。
押立神社は、小学校と隣接しています。なので小学校の校歌にもなっていて、子供たちの成長を見守り続けている神聖な場所です。豊作祭りが行なわれる春には地元から出て行った人たちが帰って賑わっています。
押立神社の辺で育ちました。小学校の校歌にも出てきます。 ずっと成長を見守られてきたようなそんな神社です。 自然も多く残り、豊作祭りには賑わいがあり、地元を出て行った人もこの祭りには戻ってくるそんな温かみのある場所です。
ご投稿頂いた内容は、当サイトのSNS公式アカウントに掲載することができます。
これらのコメントは、投稿ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、施設の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでもひとつの参考としてご活用ください。
また、これらコメントは、投稿ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容が現在と異なる場合がありますので、施設をご利用の際は、必ず事前にご確認ください。
- 前のページ
- 1
- 次のページ
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本