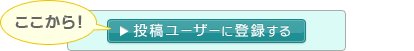まず、この神社に到達するためには、細いクネクネと曲がりくねった山道をひたすら登ってこなければなりません。途中すれ違う車も無く「本当にこの道で間違いないんか?」とちょっと不安になってします。 が、?72年に1度の【東西金砂大祭礼(磯出大祭礼)】?はここで始まります。 遥か東金砂山、西金砂山を出発した両行列は、蚫の舟(一寸法師?はたまた小人型宇宙人か?) が上陸したと伝わる水木浜付近を目指し、はるばる太平洋に向けて数十キロ、およそ10日間の大巡航を致します。 各地の御休処は、72年毎に御輿の鎮座する御旅処が設けられます。 12年毎の小祭礼でも、数百年続くと伝わる金砂大田楽舞が奉納され、各地の田楽舞会場は、大変な人だかりになります。 やがて、数日かけて常陸太田〜古代ヒラミットである石名坂一体まで行列が歩み、更に石名坂御旅処でも1泊。 風神山方向より東西の風水帰結点を結ぶ大行列となって行き、 大甕〜水木の浜〜東金沢町の旧家 金沢長者屋敷跡?日立電鉄線 大沼駅一体に田畑を開墾した100年以上前〜の日立の旧家。(金沢神社 大甕神社 弁天神社 泉ヶ森神社 神峰神社等と繋がる。) 昭和期〜平成期には、当時の金沢長者の命により、現在本家は移築?近くを通過〜 最近の大祭礼、2000年代の浜降りの際には、日立電鉄線 川原子海岸線沿いにて、田楽舞が雨天の際も、まつりを待ちきれなかった大群衆のために、盛大に執りおこなわれ、当時の橋本茨城県知事の姿や、著名人たちもあちこちで見かけられました。 大祭期間中は、茨城県におよそ100万人を超す大群衆が、祭りを訪れます。 笠松運動公園の茨城国体(1970年代)や、筑波博(1980年代)を遥かに凌ぐ、 巨大な大まつりとして、歴史に残されています。 派手さはありませんが、神懸かった神社です。 急な石段を登って奥宮の裏手にあった展望台から眺めた山々は、茨城の山、こんなにきれいだったのかと感動しました。 山頂からの眺めは残念ながら曇りがちで遠方までは、天気が良ければ富士山が見えるとか、また今度天気の良い日に参拝させて頂きます。