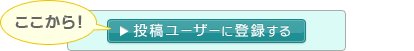御祭神 宇迦之御魂命(うがのみたまのみこと) 御由緒 天文年間、伊豆より逃れてこの地を開拓した堀越公方政知の家臣江川善左衛門雅門が、伏見稲荷大神を勧請し氏神として祀った。昭和五十年に復活した万燈神輿は、善左衛門の徳を称えた里人によって、元治年間に始まったと伝えられる。 例祭日 6月15日 所在地 〒131-0031 東京都墨田区墨田4-38-13 最寄り駅 東武伊勢崎線「鐘ヶ淵駅」 徒歩7分 京成押上線「八広駅」 徒歩7分 天文年間、伊豆から逃れてこの地を開拓した堀越公方政知の家臣江川善左衛門雅門が伊勢参詣の折、数々の厄災を8人の僧によって救われ、帰郷後、村人と合力して伏見稲荷大神を歓請し氏神としてまつったのが始まりで「善左衛門稲荷」とも呼ばれ古くは「八(はっ)僧(そう)稲荷」とも称します。旧善左衛門村(明治22年町村制施行により消滅)の鎮守社ですが荒川開削により移転しました。 往時にはこの縁起を万燈にしたてた万燈御輿でにぎわったといいますが長い中断後、近年復活されました。 天文年間(1532年〜1555年)に創建された。この地の開拓者である江川善左衛門雅門が、伏見稲荷大社から分霊を勧請し創建したものである[2]。 開拓者の名前をとって、この村は「善左衛門村」と呼ばれ、当社は村の鎮守となっていた。元々は別の場所にあったが、大正期の荒川放水路の開削により、現在地に移転した[3]。 隅田稲荷神社は、社伝によれば天文年間(1532〜55)堀越公方・足利政知の遺臣・江川善左衛門雅門が一族とともに当地に逃れて善左衛門村を開いた際、伏見稲荷より御分霊を勧請し、村の鎮守としたことにはじまるとされる。文政13年(1830)伏見稲荷より神璽を受けての帰途、美濃国で悪鬼に襲われたが、8人の僧により助けられた。これに因んで八僧稲荷とも呼ばれ、災難除けの信仰を集める。 神社は、神さまがいます。 人生何があるのかは、わかりません神様仏様! あー神様!