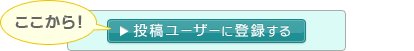場所的には、新潟市秋葉区新津本町3丁目にあります。JR新津駅より南東へ徒歩で約10分(約500メートル)ぐらいです。JR新津駅北口を出て、主要地方道新津停車場線を本町二の交差点で右折、道なりに進み、本町三の交差点を過ぎると見えて来ます。「新津跨線橋」の少し手前で左手に折れて行くと、入口があります。 堀出神社は大変由緒正しい神社です。その歴史は鎌倉時代にまで遡ります。堀出神社の発祥の地は同じ秋葉区内ですが、金津という地域があり、そこが発祥の地となります。 歴史の話になりますが、鎌倉幕府の歴史書「吾妻鏡」にも記載されていて、ボクの様な歴史好き達にとっては非常に嬉しい限りです。承久3年(1221年)5月に承久の乱が勃発すると、越後の国でも後鳥羽院の主導する王朝勢力と鎌倉幕府の執権北条義時の勢力が、この国の支配権を巡って対立し、執権北条義時は、東海、東山、北陸の三道に上洛軍を分けて編成し兵を進めましたが、その中に越後の武士で「金津蔵人資義」という人が入っておりました。この金津蔵人資義の子孫が堀出神社を造ったり、新津を創るわけです。秋葉区は元々は新津市という市でしたが、新津市の祖先を遡ると、源義家の弟源頼光(新羅三郎)の子である平賀盛義が信濃国より越後に入り、蒲原郡に平賀城(護摩堂山城)を築城し、平賀氏を名乗りました。その孫が金津蔵人資義です。昔は分家してよその土地に入ると、このその地名を姓にする場合が多かったようです。そして金津蔵人資義は金津城を造っております。社伝では「金津城築城のとき、地中から男女神像を得て城中に伊邪那岐、伊邪那美尊とお祀りし、堀出大神と奉称した。」とあります。 ちなみに、金津蔵人資義には3人の子供がいて、長男は死亡し、次男の木津左衛門尉資直が分家して金津城を継ぎ、金津蔵人左衛門尉資直と称し、金津保の地頭職となりました。三男の信資が天福元年(1223年)頃、山谷、俗に楯の腰と言われるところに分家して新津氏の初代を名乗っております(新津越前守三郎信資)。その後、両家親しく交わって来ましたが、本家の金津氏が何かの都合で金津を去る時、その所領と堀出神社の御神体を新津氏に引継ぎ、新津城内に守護神として祀られて来ました。 歴史は続いて、この堀出神社は地元の人達を中心にとても愛されております。 ボクも、昔、よくこの神社に行きました。思い出の多い神社です。