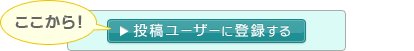松本市の西方、梓川地区の山麓線沿いにある神社です。 この神社の起源は、梓川地区のさらに西方に松本平を一望できる本神山という山がありますが、その山頂にこの地域の開拓のための守護神を祀ったのが始まりとされています。 (その神様が、梓水大神というそうです。) 北アルプスから注ぐ梓川の水は、当時から地域のまさに生命線だったことが伺えます。 その後、この神社は現在の場所に移されたそうですが、山麓線が通るこの地域は、地元では「日本アルプスサラダ街道」とも呼ばれ、野菜や果物を栽培する農家さんも多い、地域の食を支える地域です。 さて、現在の大宮熱田神社には貴重なものもありますが、特に本殿は室町時代に造られたものといわれています。 (現在は国の重要文化財になっています。) さらに境内には、長野県でも一番のモミの巨木ではないかと思われる御神木も見られます。 樹齢は600年を超えるそうで、太さも高さも相当なものです。 (こちらは、長野県の天然記念物になっています。) また後世に、合祀の神社となり、梓水大神の他に、熱田大神、天照大神、八幡大神も祀られて、さらに神社の名前も江戸時代の終わり頃より「大宮熱田神社」となったそうです。