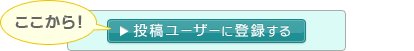仏心寺は、創建時には金台寺(こんだいじ)と呼ばれており、検非違使(けびいし、=平安時代の軍事・警察官僚)であった平諸道(たいらのもろみち)の氏寺と伝えられています。 この寺に伝わる『木造地蔵菩薩立像』は、鎌倉時代前期の貞応(じょうおう)3年(1224年)の作で、国の重要文化財に指定されていますが、通称「矢取地蔵」と呼ばれています。普通、地蔵菩薩の右手には、錫杖(しゃくじょう)を持たせますが、この地蔵菩薩は錫杖の代わりに矢を持っています。 この寺に古くから伝わる「矢取地蔵」のエピソードは大変有名で、平安時代に成立した説話集である『今昔物語集』の巻十七にも、「地蔵菩薩、小僧の形に変じて矢を受くる話」として紹介されています。 説話によれば、古来、寺の存する安孫子(あびこ)荘では隣接する押立保(おしたてのほ)との間で用水をめぐる水争いが絶えず、ある時、押立保より数百人もの大軍勢に攻め入られた際に、平諸道方は矢を射尽くしてしまい、窮地に立たされます。その時、戦場にどこからか小法師が現れ、矢を拾い集めて諸道方に与え、その矢で射たところ、思いのままに敵を倒すことができ、戦に勝利できたそうです。小法師は顔に矢を受けながらいずこともなく姿を消しました。後日、諸道が戦勝のお礼に氏寺へ参詣したところ、地蔵菩薩の顔には黒羽の矢が刺さって血が流れており、戦場で矢を拾って助けてくれた小法師はこの地蔵菩薩であったかと感じ入って、岩倉山にお堂を建てて地蔵を祀った、というエピソードです。 享徳2年(1453年)に安孫子(あびこ)の領主:鞍智高春(くらちたかはる)が寄進した『矢取地蔵縁起絵巻』(町指定文化財)も、同じ説話を題材として描かれています。 「水争い」という地域の歴史を地図の上でも、「矢取地蔵」という実像でも、立体的に体感できる施設で、また、説話を通じて庶民の願望や信仰心を感じ取ることもできる、歴史好きな方にはお勧めの施設です。