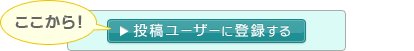金峯山寺(きんぷせんじ)は、奈良県吉野郡吉野町吉野山にある金峯山修験本宗(修験道)の総本山の寺院。山号は国軸山。開基(創立者)は役小角と伝える。かつては「山下(さんげ)の蔵王堂」と呼ばれていた。本尊は蔵王堂に安置される蔵王権現立像3躯。本尊は巨像として著名で中尊は約7mもあり、普段は非公開(秘仏)であることから「日本最大の秘仏」とも称される。現存の蔵王堂は、天正18年(1590年)に豊臣秀吉の寄進によって再建されたもので、蔵王権現立像3躯の造仏は、秀吉の発願した方広寺大仏(京の大仏)の造仏にも携わった、南都仏師の宗貞・宗印兄弟が手掛けたことが、胎内の銘から知られる。
創建年は7世紀後半頃です。
宗派は金峯山修験本宗です。
文化財としては下記の通りです。
・本堂(蔵王堂)
・二王門(仁王門)
・大和国金峯山経塚出土品1括
・金銀鍍双鳥宝相華文経箱 1合
て金銅経箱 台付 2合
附:紺紙金字法華経残闕 7紙、紺紙金字観普賢経残闕 2紙、経軸 2本
(国宝)
・銅鳥居
・木造蔵王権現立像 3躯
本堂内陣の巨大な厨子に安置される3体の秘仏。
中尊像内に天正18年(1590年)南都大仏師宗貞、宗印等の銘がある。
像高は中尊が728センチ、向かって右の像が615センチ、左の像が592センチである。寺伝では中尊が釈迦如来、向かって右の像が千手観音、左の像が弥勒菩薩を本地とし、それぞれ過去・現世・来世を象徴するという。
・木造蔵王権現立像(安禅寺旧本尊) - 秘仏本尊とは別に本堂外陣東北隅に安置される。
元は吉野山の奥の院と呼ばれた安禅寺(現・金峯神社付近にあった)の本尊で、同寺が明治の神仏分離で破却されてから金峯山寺に移された。
像高459センチの巨像で、制作は秘仏本尊より古く、鎌倉時代後半とされている。
・絹本著色千手千眼観音像 - 奈良国立博物館寄託。
・板絵著色廻船入港図額 - 万治4年(1661年)に奉納された大型の絵馬。本堂内西側に置かれている。
・木造聖徳太子立像 - 鎌倉時代。外陣東側に安置。
木造金剛力士立像 2躯 - 二王門安置。
・金銅五鈷鈴
・金銅装笈(こんどうそう おい)
・銅燈籠 文明三年銘
・梵鐘 - 永暦元年(1160年)の銘がある大型の梵鐘。東大寺の鐘(「奈良太郎」)、高野山の鐘(「高野次郎」)と並び「吉野三郎」と称される。廃絶した世尊寺の鐘で

奈良県吉野山にあるお寺、キンプセンと読み修験者・山伏などが集まる総本山。本堂は東大寺大仏殿に次ぐ大きさが有り、国宝・世界遺産に登録されてます。山の中に有り、4月の桜が満開の時期は圧倒される景色が見れます。
金峯山寺は吉野山に建つ修験道の寺院です。
修験道は仏教や神道、道教や山岳信仰などが混じりあってできた日本独自の信仰形態で、密教にも分類されます。
古くから神霊が宿るとして敬われてきた山々ごとに、修験道の性質が少しずつ異なる点が特色です。
吉野山もまた、修験道の開祖・役小角と縁があることから、霊山として信仰を集めてきました。
吉野山で修業を積んだ役小角が、蔵王権現を本尊として金峯山寺を開いたとされています。
平安時代に移ると、真言宗の僧侶・聖宝の手によって、堂宇が建てられて寺院としての形が整えられます。
その後、鎌倉時代には多くの僧兵を抱える一大勢力と化しており、後醍醐天皇と鎌倉幕府が争った元弘の乱にも登場するほど。
しかし、高師直によって焼き討ちされ寺院は焼失、再建までに多大な時間を費やすこととなります。
豊臣秀吉や徳川家康によって保護されて、本堂を含めた堂宇の再建を成し遂げるも、明治時代には神仏分離令が出されたことでまたもや大打撃を受けました。
政策転換で寺院の存続が許されると、再興の道を歩むことができるようになり、関係者の尽力のもと現在に至っています。
さて、金峯山寺の本堂の前に見事な四本桜が立っていることから分かるように、吉野山自体もまた桜の名所としても全国的に有名です。
役小角が蔵王権現の像を彫ったのが桜の木だったというエピソードから、ご神木として見なされて多くの参詣者に長年にわたって献木された結果、山全体で数万本の桜が見られるようになりました。
一方で、戦前に桜の一部をスギやヒノキに植え替えたため、現在見ることができる桜はそれ以前よりも少ないと言われています。
そこで近年になってスギ・ヒノキの伐採と、桜の植樹活動を進めており、徐々にかつての姿を取り戻しつつあるようです。
吉野山の桜を見に行きながら、金峯山寺をはじめとする寺社を参拝するというルートは春の行楽にぴったりなので、ぜひ一度試して頂きたいです。
奈良県吉野郡吉野町吉野山にある金峯山寺、きんぷせんじ。修験道の聖地として有名。日本古来の山岳信仰に、神道や仏教・道教などが一緒になり、独自の宗教として発達をとげたのが修験道らしい。その開祖とされているのが役小角。7世紀後半、小角が千日修行によって金剛蔵王権現を感得され、その姿を山桜に刻んで吉野山に祀られたことが金峯山寺の始まりと伝えられています。
平成16年に金峯山寺本堂蔵王堂及び仁王門がユネスコの世界文化遺産に登録されている。本堂には、ご本尊である三体の金剛蔵王権現をお祀りされている。他に銅の鳥居が有名で聖地への入り口といわれている。俗界と聖地の境界を象徴する建造物。東大寺の大仏を作った残りの銅で建てられたのが最初と伝えられている。他にも愛染動画が有り愛染明王がお祀りされている。手にハートを射抜く弓矢を持ち、愛を成就させてくれるという霊験がある。例祭は毎月27日にあり、縁結びのお守りも販売される。

今年の4月末、吉野山観光の際に行ってきました。
吉野山に行くのは初めてだったので、国宝で世界遺産でもあるこちらのお寺を真っ先に訪れました。
桜のシーズンを過ぎていたので、混み合うことなく観光が出来ました。
仁王門は令和10年まで解体修理中のため当分見ることは出来ませんが、秘伝のご本尊金剛蔵王大権現を拝むことができました。
拝観料は大人1,600円と少々高めでしたが、迫力満点の青色三仏(釈迦・観音・弥勒)のお姿を間近で見ることが出来た上に、お坊様の説教を聞けたり、下足用のエコバックや小さな御札まで貰えたりと、十分に満足できるものでした。

奈良県吉野山にある金峯山修験本宗の総本山になります。
世界遺産に指定されいて、詳しくはわからないですが、秘仏や国宝、重要文化財などがたくさんありますよ!
神秘的なので是非一度行かれては如何でしょうか(^^)
先日奈良県に行って来ました。奈良県をいろいろ散策し、訪れた所のひとつです。場所は奈良県吉野郡吉野町吉野山という所にあります。金峰山寺はその歴史は古く、昔歴史の教科書に出て来た役行者がここで修行した所として知られているそうで、吉野山一帯の山々が金峰山(きんぷせん)と称されて古代から聖域として知られているそうです。先程のべた役行者は修験道の創始者として知られておりここで修行を行い、以来ここは修験道の本山になったそうです。修験道と言えばやはり山伏のイメージがありますがまさにここが、山伏の聖地として現在も信仰を集めているそうです。こちらの寺院は国宝や世界遺産に指定されている建物が数多くあり見どころ満載の場所でした。なかでも本堂の蔵王堂はとても荘厳で何でも東大寺大仏殿に次ぐ大きさだそうでその高さは34mだそうです。現在のビルの高さに匹敵する建物を木材で造るという技術の高さには目が見張るものあります。国宝や世界遺産に指定された建築物は見る価値ありです。
奈良県吉野にある金峯山寺の蔵王堂は国宝と世界遺産に指定されております。
建物には秘仏・金剛蔵王大権現の尊像3体が祀られております。
ちょうど御開帳時期にご本尊を見ることができました。
とても迫力があり当時の様子がうかがえます。

奈良県吉野郡吉野町にある金峯山寺です。国宝の仁王門や蔵王堂があることでとても有名です。また全国の修験者や山伏が集う修験道のお寺としても有名です。寺院の周りは吉野さくらで有名な吉野山があり多くの観光客で賑わっていました。ぜひ皆さんも行って見て下さい。
金峯山寺は奈良県吉野郡吉野町吉野山にある修験道の根本道場。日本最大秘仏と呼ばれる金剛蔵王大権現三尊が御本尊です。吉野山の桜が見ごろを迎える春に今年は御開帳されています。高さ7mもの御本尊は大迫力です。
金峯山寺の本堂である蔵王堂は、国宝であり、世界遺産の中核資産に登録されています。単層裳階付き入母屋造り檜皮葺きで、高さ34m、裳階の四方36mの豪壮な建造物です。
創建以来、幾たびも焼失と再建を繰り返し、現在の建物は、天正20(1592)年に再建されたものです。その内部には、我が国最大のお厨子があり、秘仏のご本尊金剛蔵王大権現の尊像3体がお祀りされているほか、多くの尊像が安置されています。
金峯山寺の御本尊である金剛蔵王大権現は、およそ1300年前に修験道の御開祖である役行者によって感得された権現仏です。役行者は、全国の霊山を御開山になった後、熊野から大峯山脈の稜線伝いに吉野に修行されること33度を重ねられ、最後に金峯山山上ヶ岳の頂上で、一千日間の参籠修行をされました。苦しみの中に生きる人々をお救いいただける御本尊を賜りたいとの役行者の祈りに応えて、先ずお釈迦如来、千手千眼観世音菩薩、弥勒菩薩の三仏がお出ましに成られました。役行者は、その三仏の柔和なお姿をご覧になって、このお姿のままでは荒ぶ衆生を済度しがたいと思われて、さらに祈念を続けられました。すると、天地鳴動し山上の大盤石が割れ裂けて雷鳴と共に湧き出るが如く忿怒の形相荒々しいお姿の御仏がお出ましに成り、この御仏が金剛蔵王大権現で、役行者はこれぞ末法の世を生きる人々の御本尊と、そのお姿を山桜の木にお刻みになりました。これが、金峯山寺の始まりであり、修験道の起こりと伝えられています。権現とは、神仏が姿を変じてお出ましになった仮のお姿という意味です。金剛蔵王大権現は、役行者の祈りに応えて最初に現れられた釈迦・観音・弥勒の三仏が、柔和なお姿を捨てて、忿怒の形相荒々しいお姿となってお出ましに成られたものです。慈悲と寛容に満ちあふれたお姿と言われます。
桜のシーズンに合わせて秘仏ご開帳されています。一度のみならず二度三度と訪れたくなる神聖な寺院です。
吉野町の吉野山にあるお寺で、世界遺産に指定されています。修験道の総本山で700年ごろに金峯山に蔵王堂を造ったことが起源と言われています。境内には、国宝に指定されている「仁王門」や「蔵王堂」があり、修験道の聖地です。

修験道の聖地、【金峯山寺】は一目千本桜で有名な吉野山にあります。
国宝の仁王門と蔵王堂の大規模改修工事をしていましたが、現在特別公開中の蔵王堂の秘仏、青い大権現を見る事が出来ました。
三体の青い大権現は、その大きさや色合いの美しさは圧巻で感動しました。
桜の季節は大混雑ですが、今の時期もオススメです。
金峯山寺は、吉野ロープウェイ「吉野山」駅から徒歩10分のところにあります。拝観は、8時半から16時半です。拝観料は、蔵王堂のみ500円になります。金剛蔵王権現が特別にご開帳される時期に行かれることをお勧めします。
吉野の桜を見に行った際に立ち寄ってきました。来た目的は金剛蔵王大権現を見たかったからです。実際に見てみると、その大きさ・美しさに圧倒されました。ものすごい迫力がありました。

吉野山と共に世界文化遺産に指定されている金峯山寺は吉野山中腹の辺りにある寺院です。
千本桜で有名な吉野山内にある金峯山寺は桜の時期周りが桜に埋め尽くされ、立派なお寺と桜との景色が素晴らしかったです。

特別公開で青い三体の仏像を見ることができました。ロープウェイに乗って参拝することができます。参道には名産の葛を使ったり葛うどんのお店などが並んで賑やかな雰囲気です。
吉野山に観光に行って誰もが気付くぐらいの大きな建物が目に入ってくるのですが、それが金峯山寺です。
ケーブルカーの駅から、約10分ぐらい。観光駐車場からも約10分ぐらい歩くと、大きな仁王門が目に飛び込んできます。
地図で確認すると「金峯山寺」と書かれており、「きんみねやまでら」と読むのか「きんぷやまでら」と読むのか分からずに調べたら「きんぷせんじ」と読む事が分かりました。
では、何故こんな山の中に、これだけ大きなお寺が建立されたのか?何を目的にこのお寺が建立されたのかの疑問が湧いてきます。
このお寺は、山林修行者(山伏)の伝説的な僧侶である「役小角」が開祖とされており、山岳信仰の重要拠点とされております。
山伏は、日本の古来からあったといわれ、この金峯山寺は山伏の守り本尊とされている蔵王権現が祀られております。
このお寺の特徴として驚くのが、国宝蔵王堂の大きさです。
こちらの蔵王堂は、江戸時代の直前に再建された建物となりますが、とにかくその大きさに圧倒されます。お堂の中には、ご本尊(秘仏)である蔵王権現が3体並んでいるとの事ですが、秘仏ですので見る事はできません。しかしながら、令和2年の10月16日〜11月30日の短い期間ではありますが、特別拝観で見ることができます。私は、当時愛犬を連れての旅でしたので、見る事はできなかったのですが、この期間に行かれる方は拝観された方が良いと思います。
話は、こちらのお寺の歴史に戻りますが、江戸時代に入り、徳川家康の命により、江戸時代の伝説的な僧侶である「天海上人」が管理した史実も残り、この頃は天台宗のお寺となった歴史もあります。
その後、時は流れ太平洋戦争が終わり、日本が復興の歩みを始めた昭和27年に天台宗から分派した「大峯修験宗」が創設され、現在に至っております。
現代において、山伏を見る事は、霊山と言われるエリアでしか見る事はないのかも知れませんが、この金峯山寺には山岳信仰が受け継がれる重要な場所となっております。

金峰山寺は、奈良県吉野郡にある寺院です。本堂は国宝に認定されております。3月に初めて訪れたのですが、本堂はとても圧倒されました。ちょうど桜が咲き始めた頃でしたが、満開にはなっておらず、今度は満開の頃に行きたいです。
金峯山寺(きんぷせんじ)は、吉野山のシンボルであり修験道の総本山です。蔵王堂は、東大寺大仏殿に次ぐ木造大建築物です。金峯山寺は、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」の中核的資産として世界遺産に認定されています。
金峯山寺は奈良県吉野町にある寺院です。奈良に旅行に行った時に立ち寄りました。1300年前に役行者が開いた古刹。先ず国宝に指定されている蔵王堂の雄大さにびっくり。次に7mの巨大な金剛力士像に圧倒されました。南北朝時代に南朝の拠点にもなっていて歴史を感じることができました。
先日、金峯山寺にいってきました。初夏の吉野山への観光で立ち寄ったのですが、とても大きな金剛力士像が大迫力で圧倒されました。建物の改修中でしたが中はみることができました。本堂も大きな建物で威厳があり、そこからの眺めもよいのでしばらく心地の良い時間を過ごせました。吉野は桜の季節のイメージがありますが、初夏もおすすめです。

この施設は、奈良県吉野山内に有ります。
世界文化遺産に登録されています。
いつも観光される方々が多いのですが
特に、春と秋はとんでも無い位人・人・人です。
その中には、外国の方もおられます。
一度、行かれてはいかがですか。

「一目千本桜」で有名な奈良吉野 に世界遺産の 國軸山 金峯山寺 があります。まず出迎えてくれる国宝の仁王門の中の金剛力士像は東大寺の仁王像につぐ大きさだそうです。参拝料を収めると靴袋がいただけるのですがしっかりしていてまるでエコ袋のようでした。

金峯山寺は、世界遺産に登録されており、国宝の「蔵王堂」をはじめ、歴史ある建築物が数多くあります。
蔵王堂のご本尊は「日本最大の秘仏・金剛蔵王大権現」で、特別にご開帳される期間があります。
青い顔が特徴の秘仏です。
南北朝時代の「南朝・後醍醐天皇」が本拠とした場所でもあり、歴史を感じる遺跡がたくさんあります。

飛鳥時代のお寺です。3体ある仁王像は7mを越える大きさで、全てを見透かしているかのような視線と表情。お寺は仏像の撮影ができない所がほとんどで、こちらもそうでした。
金峯山寺から西に下っていくと、吉野朝宮跡や、妙法院、脳天大神龍王院などもありました。
世界遺産に登録されています。観光客や修学旅行生等で賑わっています。訪れた時は特別開帳の時ではなかった為まだ見たことがないのですが、千手観音、弥勒菩薩、釈迦如来の秘仏があります。特別開帳の際にしか見ることはできないので、今年はスケジュールを合わせて行きたいと思っています。
金峯山は吉野桜が大変美しいことでも有名です。桜の季節以外でも境内からの景色は大変素晴らしいです。金峯山寺や吉水神社を含む一帯は「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されてます。境内で最も古い国宝仁王門は圧巻です。
吉野山の途中にある金峯山寺(きんぷせんじ)は、役行者が開いた修剣道の総本山です。美しいカーブの屋根で重層入母屋造りの蔵王堂は荘厳で素晴らしいです。圧倒的迫力の金剛蔵王大権現は特別公開で拝観できます。

吉野桜で有名な金峯山寺。
場所は奈良県は吉野山にあります。
こちらのお寺には珍しい秘仏「青い三体の蔵王権現」が奉られており、平成30年5月6日まで「国宝仁王門大修理勧進秘仏ご本尊特別御開帳」が公開されていると聞きつけ拝観に参りました。
九十九折の吉野山をかけあがり、過ぎてしまった桜を眺めつつ金峯山寺に向かうと、まず「黒門」があります。土産物や旅館街を抜けてちょっとした広場のような空間に佇む「銅の鳥居(かねのとりい)」を抜け、柿の葉寿司を販売するお店が並ぶ道を抜けると、仁王門にたどり着きます。残念ながら国宝に指定されている「仁王門」は、仮囲いに覆われており、その姿を見ることは出来ませんでした。しかし仁王像を薄明かりの中を窺うことはできました。
拝観受付所で拝観料を納めて、ご朱印受付所でご朱印をお願いします。なんと、特別ご開帳期間は、期間限定で蔵王権化を連想させる青い台紙に金の文字のご朱印も選べます。
そしていよいよ、秘仏本尊がある「蔵王堂」へ。ご開帳期間は記念の御札と下足用の手提げ袋を頂いて拝観します。(もちろんお堂の中は撮影禁止)
青い大きな三体の「蔵王権化」という弥勒菩薩(未来)、釈迦如来(過去)、千手観音(現世)の荒ぶるお姿を見上げてただただ放心するばかり。また個別に拝むことが可能な「発露の間」という障子に囲われたスペースで、一組ずつ静かに向かい合うことが出来てとても貴重な体験でした。
護摩壇を眺めて蔵王堂をぬけ渡りを抜けた本地堂では、吉野山の写真展と共に、通常のお姿の弥勒菩薩、釈迦如来、千手観音の立像のほか、開祖「役行者(役小角)」の像があり、手前にある木製の三鈷杵に触れることも出来ました。
蔵王堂を後にして境内中央の4本桜から改めて蔵王堂をながめるとその荘厳な造りと美しさにため息が出ました。振り返って吉野の山々の風景も修験道の聖地としてあるこの山一体を包む空気に触れ、すがすがしく下山いたしました。

奈良県吉野山の途中にあります『金峯山寺(きんぷせんじ)』と読みます。ここの秘仏の青い釈迦如来、弥勒菩薩、千手観音菩薩の3体がすごい顔で私たちを見ています。有料ですが、この菩薩に懺悔をすることで心が軽くなるかもしれません・・・。とても迫力のある秘仏です。
役行者(えんのぎょうじゃ)が開いたとされる
金峯山寺(きんぷせんじ)は世界遺産に登録されています!
こちらには日本最大秘仏がいらっしゃいます。
釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の三体が秘仏です。
普段は公開されていませんが
ご開帳される時がります。
今年は3月の末から5月5日まで特別ご開帳です!
必見ですね

世界遺産 吉野山の下千本真ん中辺りにある蔵王堂と呼ばれる大きな本堂を擁する寺院です。建物の大きさにただただ圧倒されるこのお寺も世界遺産登録されています。吉野のシンボルの様な存在です。
世界文化遺産の金峰山寺は建物に圧倒されるお寺です。特に仁王門は迫力があり、時代を感じられ、なんだかパワーをもらえるような建物です。桜の時期は人が混雑するので、考えて行動する事をオススメします。

修験道の改組、役行者が金峯山で修行し、人々を悟りに導くために開いたとされるお寺です。金峯山寺や吉水神社を含む一帯は「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されてます。大迫力の木造建築には圧倒されます。境内で最も古い国宝「仁王門」は現在、大修理が行われてます。
奈良県吉野郡にある金峯山寺は山伏修行の寺として有名です。
岸壁でお子なられる捨身の行は目を見張るものがあります。
そしてここには重要文化財の金剛蔵王権現があり毎年一定期間のみ見ることが出来ます。境内から見える景色も神秘的ですよ。
吉野の山中にそびえる金峯山寺は山岳修行のお寺として有名です。西の覗きと呼ばれる断崖の上で行なわれる捨身の行や福は内、鬼も内と唱える節分会など独特な行事があります。

世界文化遺産の奈良県吉野町の金峯山寺へ行ってきました。
世界文化遺産なので、大変多くの人で混雑しているのかと思いました、混雑などしていなく、大変静かな中、ゆっくりと楽しむ事が出来ました。
私が特に目を引いたのが仁王門でした。
その大きさ造りに圧倒されました。
周囲は山々に囲まれ、自然に囲まれた中にあり、自然に囲まれた中にある為に少々遠いですが、行く価値は大いにありました。
次回は季節を変えて行ってみたいです。

金峯山寺は世界遺産にも登録されています。期間限定にはなりますが特別拝観では秘仏本尊が拝見することができます。また大峰修行体験が5月から10月におこなわれております。最近ではブームになっている朱印帳は行者さんのデザインのものもあります。
世界遺産であるこのお寺は、桜の名所、奈良県吉野山の中腹に位置し、連日たくさんの観光客が訪れています。
とにかく大きなお寺で、すごい迫力でした。
海外からわざわざここを目指して来る方もいます。

桜の名所として知られている吉野山のある金峯山寺。
私も桜の時期にハイキングがてらに吉野山に来たときに立ち寄りました。
遠くからでもお寺の矢根が大きく見え、桜ととても合う光景です。
立派な本殿で、日本最大秘仏本尊も特別拝観もちょうど公開あれていました。
とても風情のある、世界文化遺産の金峯山寺です。

吉野山の紅葉を見に出掛けた際に、世界遺産の金峯山寺蔵王堂の秘仏御本尊が開帳されていましたので拝観して来ました。
全身が青に塗られた三体の仁王像は大きくて神秘的な雰囲気を醸し出していました。
有名なのが金剛蔵王大権現の三体の像ですね。
ご開帳の期間しか見ることは出来ないので、日程はしっかりチェックして行った方がいいです。
何年か前に合わせて行った事がありますがものすごい人だかりでした。
青い色が映えて大迫力!
パワーをもらえました!
世界遺産に登録されているという事で先日友人と行ってきました。日本最大の秘仏を本尊とする修験霊場だそうで、本尊の眉を吊り上げ、目と口をカッと開いたお顔は迫力満点です。

桜で有名な奈良県吉野山の下千本に位置しています。
山の中にある感じでしたが、とにかく大きいです。
圧倒されました。
本堂の蔵王堂は重層入母屋造りと言うそうです。
秘仏本尊蔵王権現三体のほか、多くの尊像を安置されています。

御開帳で、1,000円を納めて、結界に入って金剛蔵王権現を間近に拝んできました。鮮やかな青色、仏像の大きさに圧倒されました。拝む場所にはがきがあり、持ってかえって、後日、願い事などを書いて送ります
靴をいれる袋は、持ち帰れるようにお寺をデザイン化したマークの入ったお洒落な袋がいただけます。その他に、お札もいただけます。
山岳信仰の聖地で、いくつもの神社仏閣がありますが、このお寺はとても歴史があり、すばらしい建築物がたくさんあります。お寺なのに鳥居がありまして、文化財です。仁王門は重厚で、すんばらしいです。信仰対象となっている蔵王権現は、仏教と伸道とは立ち居地が違う独特の神様(仏?)で、珍しいご容姿なんで、ぜひナムナムと拝んでください!

平成24年より10年間の予定で1年のうち一定期間、蔵王堂大権現さまのご開帳が実施されています。平成24年のJR東海のテレビCMで青くて大きな大権現さまは印象的でした。春には吉野山が桜で彩られるのでおすすめの季節です。駐車場は吉野山観光駐車場を利用。桜の季節の週末は人気で早々に満車になるので注意が必要です。
これらのコメントは、投稿ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、施設の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでもひとつの参考としてご活用ください。
また、これらコメントは、投稿ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容が現在と異なる場合がありますので、施設をご利用の際は、必ず事前にご確認ください。