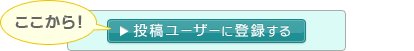第八番札所 普明山 熊谷寺真光院へ行ってきました。 山門から大師堂まで400mの登り道があります。ちなみに山門は徳島県指定文化財になっています。本堂には金色の千手観音もあります。四国で一番古い多宝塔も趣があって良いですよ。 第七番十楽寺から、徳島自動車道に沿って走る川を渡り、土成インターチェンジを過ぎると、やがて道は国道318号線と交差します。この近くには名湯として知られる御所温泉があり、国道を越えたあたりから、道沿いには緑の木々が繁り、心を誘う木影をつくっています。自然の風光を楽しみながら、さらに1kmほど行くと右手に第八番熊谷寺。簡素な造りだがその迫力は圧巻の山門が見えてきます。 仁王門をくぐるとすぐに収経所がある方丈、その隣には駐車場があります。本堂や大師堂のある山の中腹部は、ここからさらに長い石段や坂道を登った先にあります。 歴史と由来ですが、弘仁6年 (815年)、弘法大師が熊谷山で修行したとき、紀州熊野権現が出現し、1寸8分 (5.5cm) の黄金の観音像を授けたといいます。そこで大師は等身大の千手観世音菩薩を刻み、その胎内に権現様より授かった観音像を納め、堂を建立して安置したと言います。これが、熊谷寺の発祥にまつわる不思議な伝説です。 大師が修行した山中には、やがて堂塔がつぎつぎ建てられ、貞享4年(1687年)には四国霊場のなかでも最大といわれる楼門も完成し、立派な寺観を整えるようになったそうです。山中にあったために、戦国時代の兵火にもさほどの被害は受けなかったのですが、残念なことに、本堂は昭和2年 (1927年) の火事によって焼失。現在の本堂は、昭和47年 (1972年)に再建されたものです。 利益とエピソードとしては、境内の納経所の前にある弁天池の中央にぽっかりと浮かぶ弁天島に祀られているのは弁天様です。これは、もともと大師堂の池にあったものを昭和初期にこちらに移したもので、その歴史は古く、昔から安産に霊験があるといわれ、多くの女性参拝客が訪れています。 みどころと食事処ですが、やはり一番の目玉は、 四国八十八ヵ所寺院のなかでは最大といわれる山門ですね。高さ13mで2階、天井には妖艶な天女が描かれています。境内の最深部にある多宝塔も必見です。四国で一番古いといわれる室町時代の建造で、大日如来など5体の仏像が安置されています。