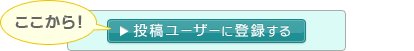青梅市千ケ瀬町にある「千ヶ瀬神社」は、JR青梅線「東青梅駅」南口下車、徒歩約10分くらいのところにあります。 千ヶ瀬神社は、古くは大社権現、江戸時代には稲荷社と称していたそうです。千ヶ瀬村の鎮守で、社家の先祖・出雲太郎某が故郷・出雲の杵築大社(出雲大社)の上を勧請し、出雲神社と称したことに始まると伝えられているそうです。明治7年(1874)村内の神明大神宮(神明社)を合祀し、明治16年(1883)千ヶ瀬神社と改称したそうです。 創建年代は不詳ですが、社家・高野氏の家伝によれば、今から一千年ほど前、先祖の出雲太郎某によって創建されたと言われています。出雲太郎は出雲国杵築大社(現在の出雲大社)の社人の次男であったが、故あって東国に下ったそうです。当地に住み着いて杵築大社の神を勧請し、出雲神社と称したのが当社の起こりといわれておます。 明治元年(1868)閏4月13日、有栖川宮へ神明・稲荷両社の名で道中安全祈祷の玉串を献上し、明治3年(1870)稲荷神社と改称、明治6年(1873)村社に列格。明治7年(1874)御伊勢山(『青梅市史』では御伊勢林)にあった神明大神宮(神明社)を境内に遷座し、明治16年(1883)両社を合わせて千ヶ瀬神社と称するようになったといわれています(※千ヶ瀬神社でいただいた由緒書に従う。『青梅市史』等では明治15年9月となっている)。 大正15年(1926)社殿を再建したといわれております。 また千ヶ瀬神社には、社殿の東西に出雲太郎が植えたと伝えられる御神木の椎の木があり、それぞれ朝日の御蔭、夕日の御蔭と呼ばれております。残念ながら夕日の御蔭は文明12年(1480)大風で折れ、枯れてしまったそうです。現在のものはその後に植えられたものだそうです。朝日の御蔭は現在も青々と茂り、昭和32年(1857)青梅市の天然記念物に指定されております。 また中には御朱印を集められている方もいるかと思いますが、「千ヶ瀬神社」でも頂く事ができます。御朱印は宮司様宅にて拝受できるそうです。(※社務所に案内図あり) 皆様も是非お近くに来た際は、心安らぐ「千ヶ瀬神社」へ一度立ち寄ってみてください。