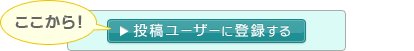常滑市金山屋敷の、幹線道路から1本入ったところにあります。この地域に古くからあるお寺です。真言宗智山派に属する由緒ある寺院で、知多四国霊場第66番札所として信仰を集めています。静かな山間にたたずむこの寺は、訪れる人々に心の安らぎと厳かな雰囲気を提供してくれる場所です。 歴史としては、戦国時代の天文年間(1532年〜1555年)にまでさかのぼります。当時、大野城主の祈願所として建立されたと伝えられています。もともとは「金蓮寺」の一坊であり、「能見寺中之坊」と称されていました。しかし、1584年(天正12年)の九鬼水軍による大野城攻撃の際に、金蓮寺とともに焼失。その後長い年月を経て、明治30年(1897年)に再興され、現在に至っています。 お寺の本尊は、平安時代の仏師・春日定朝作と伝わる「十一面観世音菩薩」です。観音菩薩は慈悲の象徴として知られ、あらゆる人々の願いを聞き入れ、救済すると言われています。 また、寺には全身が黒色の「黒弘法大師」が祀られています。この黒弘法大師は、鋭い眼差しで邪気を払い、特に悪病除けや子供の虫封じに霊験あらたかとされ、地域の人々の厚い信仰を集めています。 中之坊寺には、貴重な仏教美術が数多く残されています。その中でも特に重要なのが、国指定文化財の「絹本著色仏涅槃図」です。この涅槃図は、釈迦の入滅の様子を描いたもので、仏教美術の歴史を伝える貴重な資料とされています。その他にも、両界曼荼羅、十六善神図、愛染明王図など、歴史的価値の高い仏画が所蔵されています。 また、境内には「タラヨウの木」が植えられています。この木の葉の裏に傷をつけると文字を書くことができるため、「ハガキノキ」とも呼ばれています。昔は手紙代わりに使われたこともあり、現在では学問成就や知恵を授かる木として親しまれています。 このお寺は、常滑市の自然に囲まれた静かな場所にあり、公共交通機関でのアクセスは限られていますが、車での訪問が便利です。常滑観光の際に、四国霊場巡りの一環として訪れるのもおすすめです。 このお寺は、知多四国霊場の一つとして、歴史的価値が高く、文化財も豊富に所蔵する魅力的な寺院です。本尊の十一面観音や黒弘法大師への信仰、貴重な仏教美術の数々、そして自然に囲まれた静寂な環境が訪れる人々を魅了します。歴史と信仰に触れることができる中之坊寺を、ぜひ一度訪れてみてください♪