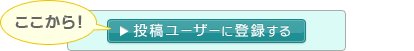山梨県甲府市にある来光寺(らいこうじ)は、日蓮宗に属する古いお寺で、室町時代の永享年間(1429年〜1441年)に名僧の日遠(にちおん)によって開かれたとされています。 日遠は甲斐の地で熱心に布教活動を行い、その教えに共鳴した多くの信者が集まりました。 そして、日蓮宗の信仰と学びの拠点として発展していったそうです。 来光寺は、戦国大名の武田信玄とも深い関わりがあります。 武田信玄は日蓮宗の教えに深い信仰を持っていて、領国経営にも仏教的な価値観を取り入れていました。 そのため、信玄は来光寺に多くの寄進を行ったそうで、お寺の発展を支えました。 寺院には信玄が寄進した品々や、武田家ゆかりの史料が残されており、戦国時代の甲斐の歴史を知る重要な場所となっています。 境内には信玄の側近や弟子たちの供養塔が並んでおり、武田家との関係が確認できます。 江戸時代には、甲斐の地は幕府の直轄領となりましたが、来光寺は引き続き地域の信仰の中心として栄えました。 日蓮宗の学問所としても知られ、多くの僧侶がここで学んでいたそうです。 また、来光寺では年中行事や季節ごとの儀式が行われ、地域住民の心の拠り所としての役割を担ってきました。 明治時代の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)によって、多くの寺院が打撃を受けるなかで、来光寺は地元の人々の支えを受けて存続しました。 現在も来光寺は、地域の人々にとって大切な寺院であり続け、春には桜、秋には紅葉が楽しめる観光スポットとしても人気です。 最近は、武田信玄ゆかりの地として、歴史好きの訪問者の方も多くいるようで、私が訪れた際にも20代くらいの女性が3人で参拝をしていました。 来光寺の歴史は、日蓮宗の教えの広がりと甲斐の地域文化、武田家の信仰に支えられてきました。 創建から約600年、お寺は多くの歴史的な出来事を乗り越えながら、今もその伝統を大切に守り続けています。 ぜひ一度、訪れてみてはいかがでしょうか。