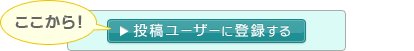福井県大野市の静かな山間部、木本という自然豊かな地区にひっそりと鎮座しているのが高尾磐倉神社です。訪れたのは春先の新緑の季節で、鳥のさえずりとやわらかな風に包まれながら、山道を歩いて向かいました。車が通ることも少ない場所で、まるで時間が止まっているかのような感覚を味わえます。 神社へ向かう途中、案内板のようなものが立っており、「磐座(いわくら)」という言葉が目に入りました。磐座とは、神が宿るとされる岩や巨石のことで、日本の古神道における信仰の原点でもあります。つまりこの神社は、社殿よりも古く、自然そのものを神として祀る「原初の神社」なのです。 鳥居をくぐり、杉の木立の中を進んでいくと、やがて目の前に現れるのは、苔むした大きな岩々と、それを囲むように設けられた素朴な社殿。まさに「磐座」という名にふさわしい景観です。人工物というより、自然の力そのものがご神体となっていて、神秘的な空気が漂っています。こうした形で神を祀る神社は、全国的にも少なく、非常に貴重な存在です。 高尾磐倉神社の歴史はとても古く、創建は奈良時代以前ともいわれています。文献や伝承は少ないものの、地元の人々の間では長く信仰の対象とされてきました。特に農業の神、山の神、水の神としての信仰が強く、昔は五穀豊穣や雨乞い、山仕事の安全を祈るために多くの村人がここを訪れていたそうです。 また、この神社のある地域は、古くから修験道とも関わりがあり、山岳信仰の一環として修行僧たちが磐座で祈りを捧げていたという話も残っています。神社の近くにはかつて行者道があり、山伏たちが身を清め、自然と対話しながら修行を重ねていたと伝わっています。 社殿自体はとても小さく、豪華さはありませんが、木の香りがただよう拝殿に立ち、目の前の磐座に手を合わせると、自然と心が静まり、自分が自然の一部であることを実感します。まさに“神と自然が共にある場所”といった印象でした。 帰り道、地元のおじいさんと少し立ち話をしたのですが、「昔は子どもたちがあの岩のまわりで鬼ごっこしてたんだよ。でも、ちゃんと“岩の神様に失礼のないように”って言ってからね」と笑いながら話してくれました。信仰と日常が自然に結びついている地域の暮らしが感じられる、なんともあたたかいエピソードでした。