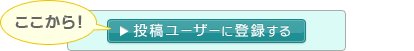福井県越前市北小山の田園地帯の中、ひっそりと佇む野々宮神社は、都会の喧騒から離れて心がほっとするような、地元の人々に長年親しまれてきた神社です。私が訪れたのは、秋の初め。稲穂が黄金色に輝き始めた頃で、神社の周囲に広がる田んぼや山々の風景が本当に美しく、まるで絵のようでした。 神社へと向かう道は、古くからある細い農道を抜けた先にあり、目の前に見えてくる朱色の鳥居がとても印象的でした。鳥居をくぐった瞬間、空気がすっと変わったような気がして、思わず背筋を伸ばしてしまうほど。境内はこぢんまりとしながらも、よく手入れされていて、地元の人々が大切に守ってきたことがすぐに伝わってきました。 さて、この野々宮神社の歴史はとても古く、創建は平安時代ともいわれています。その名前からもわかるように、「野々宮(ののみや)」という言葉は、かつて皇女が伊勢神宮に仕えるために身を清めた「斎宮(さいぐう)」に由来するとされています。実際には京都の嵯峨野にある野宮神社が有名ですが、各地に「野々宮」という名を冠した神社が存在しており、ここ越前の地でも古くから清浄な祈りの場として人々の信仰を集めてきたと考えられています。 御祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)で、太陽の女神として日本神話に登場する非常に重要な神様です。また、五穀豊穣、家内安全、無病息災など、暮らしに関わる様々なご利益があるとされ、農業の盛んなこの地域では、昔から農作業の始まりと終わりに人々が手を合わせてきたそうです。 境内の奥には、木々に囲まれた小さな本殿があり、苔むした石段を上ると、その静けさと荘厳さに思わず息をのむほど。杉の木立の中にひっそりと佇むその姿は、まるで自然と神様が一体となったような神聖な空気をまとっていました。 地元の方に聞いた話では、毎年10月に秋の例大祭が行われ、今でも集落の人々が集まり、神輿の巡行やお囃子の演奏が奉納されるそうです。規模は大きくないけれど、地域の絆が感じられるあたたかなお祭りだと聞いて、今度はその時期にまた訪れてみたいなと思いました。 また、神社の周辺には、古墳跡や石仏など、歴史的な見どころも点在していて、この地域全体が昔から人々の営みと信仰が深く結びついてきた場所であることが感じられました。