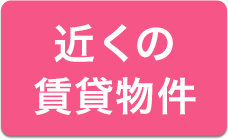「常栄寺」から直線距離で半径3km以内の観光スポット・旅行・レジャーを探す/距離が近い順 (1~106施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックすると常栄寺から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックすると常栄寺から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉の大町にある八雲神社です。 鎌倉駅から徒歩10分くらいのところにあります。 入口の看板に「祇園山ハイキングコース」とも書いてあったので、ハイキングコースの一部のようです。 一つ目の鳥居をくぐると手水舎があり、その先の二つ目の鳥居をくぐると本殿前の境内に出ます。「鎌倉最古の厄除の社」と書いてある看板があったので歴史のある神社のようです。 神社の略記を読むと永保時代に新羅三郎源義光公が勧請と書いてあるので平安時代から続いているようです。 御神木の根元に「新羅三郎手玉石」というのがありましたが説明書きが無かったので、どのような言い伝えがあるのかが気になりました。 境内はとてもきれいに手入れがされており、清々しい気持ちになりました。 また真っ赤な厄除け祈願の旗がたくさん立てられていたのがとても印象的でした。 宝蔵殿には四基の御神輿が保管されており、盛大なお祭りが行われるのだろうと思いました。 後で調べると毎年7月上旬に例大祭が行われ、神輿振りは圧巻と書いてありましたので、今度見に行きたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 小町大路沿いに境内を構える日蓮宗の寺院、本覚寺を参詣しました。 源頼朝が御所の鬼門の守護のために建立した夷堂があった場所に建てられた寺院ということで知られる本覚寺。夷堂は今の山門前にあったと伝わります。今は境内に昭和56年に再建された夷堂を見ることができます。 仁王門をくぐり境内に入ると右側に夷堂、正面に本堂があります。本堂を右側に進むと日蓮の分骨を祀る日蓮御分骨堂を見ることができました。 そのほか、応永17年(1410年)の銘が入った梵鐘が吊るされた鐘楼や鎌倉時代末期から南北朝時代初期に活動した刀工、岡崎五郎正宗のものと伝わる墓所がありました。 朝のうちに訪れたので境内はとても静かでゆっくりと参詣することができました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉にある雪の下教会は、私が子供の頃からずっとあるカトリックの教会です。段葛に面している若宮大路の道にあります。 大正6年1917年に伝道が始まり、昭和16年1941年に鎌倉カトリック雪の下教会になったそうです。思っていたより歴史のある教会でした。昔、妹がこの教会で活動する合唱団に所属していましたので、よくこの教会で合唱を聴きました。定期的にバザーなども開催しています。 この教会は、とても大きな教会で、中はすっきりしていてとても美しい建築です。光の入り具合も神秘的で、厳かな気持ちになります。 なんとパイプオルガンもあります。演奏している時に遭遇できればラッキーです。とてもいい音色のオルガンです。 教会正面の上部には聖母マリアのモザイク画があります。素敵な教会であることを感じます。 そして、この教会では結婚式を挙げることもできます。結婚の講座を受けることや、司祭と面談する必要がありますが、とても厳かな結婚式になりそうですね。日曜日以外で実施できるようです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉駅から徒歩10分くらいのところにあるお寺です。 鶴岡八幡宮を右に曲がって少し進んだ突き当りにあります。 参道に入って直ぐのところにある看板を読んでみると、新田義貞の鎌倉攻めで滅亡した北条氏の霊を弔うために後醍醐天皇が足利尊氏に命じて建てられたようです。 更に参道を進むと本堂前の開けた境内に着きます。 とてもきれいに手入れがされており、清々しい気持ちになりました。 また、本堂の横にある大きなイブキの木がとても印象に残りました。 参道の両側には御堂や慰霊碑が幾つか建っており、一番奥の御堂が大聖天のものだったので、入口にあった「大聖天」の大きな石碑に納得しました。 本堂の中には沢山の仏像が祀られており、厳粛な雰囲気だったので緊張してしまいました。 後で調べて分かったのですが、「萩寺」という名前でも親しまれているようなので、秋のお彼岸時期にまた訪れてみたいと思います。
-
周辺施設常栄寺から下記の施設まで直線距離で755m
鎌倉市鏑木清方記念美術館
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉市鏑木清方記念美術館は、日本画の巨匠、鏑木清方の作品をじっくり鑑賞できる美術館です。清方の繊細で美しい筆致を間近で堪能でき、彼の作品に込められた歴史や文化の深さを感じることができます。展示スペースは落ち着いた雰囲気で、静かに作品と向き合うことができます。また、館内には清方の生涯や業績に関する情報も豊富に展示されており、彼の芸術に対する理解を深めることができます。鎌倉の観光と合わせて訪れるのがおすすめです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 神奈川県鎌倉市にある神社鶴岡八幡宮。別名鎌倉八幡宮と呼ばれる事もあり、八幡宮と呼ばれる神社の中でも特に有名で、聞いた事がある人も多いのではないでしょうか。 鎌倉時代からの長い歴史を持つ鶴岡八幡宮ですが、鳥居へと続く道はとても開けており、周辺の街の作りが鶴岡八幡宮の為に作られています。街のシンボルとも言え、鎌倉を知る上で重要な施設である事が分かります。 見所はやはり国の重要文化財にも指定されている本宮。年間を通し、様々な祭事を行なっています。鳥居越しに道からみても分かる圧倒的な存在感は、鶴岡八幡宮と言えばと言える程の素晴らしい情景です。 アクセスは是非若宮大路と呼ばれる参道を歩いてみるのが良いと思います。参道は2キロメートル程度の長い道ですが、その道のりも含めて楽しむ事ができます。 鎌倉観光には必ずと言っても良い程名前が上がる鶴岡八幡宮。是非鎌倉へ訪れる際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。鎌倉の文化に触れる事ができると思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉を訪れた際に、長年一度は見てみたいと思っていた鎌倉大仏(高徳院)を訪れました。写真では何度も見たことがありましたが、実際に目の前に立ってみると、その大きさと存在感に圧倒されます。高さ約11メートル、重さ約121トンとされるこの青銅製の阿弥陀如来像は、想像以上の迫力で、静かに佇むその姿からはどこか温かさと厳かさが同時に伝わってきました。 大仏は屋外に設置されており、青空や季節の風景と調和してとても美しいです。私が訪れた日は晴天で、青空を背景にした大仏の姿はとても写真映えし、観光客も多くカメラを構えていました。外国人観光客も多く、世界中からこの地を訪れていることが感じられました。特に欧米やアジアからの旅行者が多く、世界的な観光地としての魅力を改めて実感しました。 参拝料は大人300円と良心的で、さらに追加料金(20円)で大仏の胎内(内部)に入ることもできます。内部は狭いですが、鋳造の構造や補強の跡などが見学できて、とても興味深い体験でした。外からは想像もつかない、内部構造の工夫や歴史を感じることができ、より一層この大仏への敬意が深まりました。 高徳院の敷地自体はそれほど広くはないものの、静かで落ち着いた雰囲気があり、自然に囲まれた環境も魅力的です。大仏の背後には緑の木々が広がり、春は桜、秋は紅葉と、季節ごとに違った表情が楽しめるそうです。また、大仏の前にはベンチがあり、ゆっくり腰掛けて眺めることもできます。時間を忘れてしばらく佇んでいたくなる、そんな穏やかな空間でした。 アクセスについても、鎌倉駅から江ノ電に乗って長谷駅で下車し、そこから徒歩約10分ほどと便利です。駅からの道のりも観光地らしく、土産物屋やカフェが立ち並び、散策するのが楽しいエリアです。途中で食べた鎌倉名物のしらす丼や、和菓子店で購入した抹茶羊羹も旅の良い思い出になりました。 さらに、大仏見学の後には近くの長谷寺や由比ヶ浜にも足を延ばすことができ、1日で鎌倉の魅力をぎゅっと楽しめます。歴史好きの方はもちろん、カップルや家族連れにもおすすめのスポットです。 鎌倉大仏はただ大きいだけでなく、その穏やかな表情、歴史的背景、そして人々に寄り添うような空気感がとても印象的でした。ぜひ一度、自分の目でこの大仏の優しさと迫力を体感してみてください。期待を裏切らない、心に残る観光体験になるはずです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- JR横須賀線、北鎌倉駅から3分ほど歩いたところに、円覚寺があります。 開基は北条時宗公のお墓です。 お祀りされているのは、北条時宗公、その子供で鎌倉幕府九代執権の貞時公、その孫で鎌倉幕府十四代執権、高時公をお祀りしています。 二度にわたる蒙古襲来という未曾有の困難に立ち向かった時宗公は、その戦いで亡くなった死者を敵味方関係なく供養するために中国から佛光国師を招き1282年に円覚寺を開山しました。 国師の禅の教えに深く帰依した時宗公は、この場所で禅の修行を行ったと言われております。1284年に時宗公が亡くなると、その庵のあった場所にお堂を建てました。 鎌倉幕府が終わると次第に衰退しましたが、室町時代の末期に北条氏の庇護を受けた鶴隠周音禅師(かくいんしゅういん)がお堂の南側に玉泉軒を建てた(後に佛日庵と改める)のち円覚寺の塔頭として再び繁栄させました。 現在のお堂は江戸時代に改築されたもので時宗公、貞時公、高時公の木像は鎌倉仏師により修理されています。 毎年の4月4日には円覚寺山内の和尚様方が集まり、毎年忌の法要が執り行われます。 また、8月15日には時宗公、貞時公、高時公のご供養の法要が執り行われます。 ハイキング目的で来ても楽しめる和の景色があります。 庭園を眺めながらお寺に向かうといつのまにかお寺まで歩いてしまいます。上からの景色も楽しめますよ。 周りを見ると多くの外国から来た家族や、カップルが感激しながら写真を撮っていました。鎌倉時代を想像しているのかもしれません。 新緑の季節は緑が多いですし、紅葉の時期は真っ赤に染まって眺めが最高です。 ぜひ行ってみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 「鎌倉宮」という名前が気になったので先日行ってきました。 鎌倉駅から鶴岡八幡宮の方へ進み、入口を右に折れてから15分ほど歩いたところにある神社です。 入口の前が少し開けていて、その中心にある笠木の部分が赤く塗られた白い鳥居がとてもきれいで印象的でした。 鳥居をくぐると開けた参道になっており、本殿前にも入口と同じ白い鳥居があって更に神聖な雰囲気を感じました。 由緒書きによるとこの神社の創建は明治2年で、鎌倉時代に活躍された後醍醐天皇の皇子である護良親王を祀っているそうです。 手水舎に行くと、水場の回りにかわいらしい獅子舞の頭の部分がたくさん置かれていたのでとても興味深かったです。後で調べて分かったのですが、護良親王が出陣の際に兜の中に入れていたと伝えられているようで、災いを食べて幸せを招くとされる人気のお守りのようです。 また手水舎の向かい側には「厄割石」があり、小皿に息を吹きかけて投げつけて割ると厄を祓えるようです。あまり見たことが無かったのでとても興味がありましたがやらずに帰ってきたので少々後悔しています。 全体的に手入れが行き届いていて本殿もとてもきれいで、清々しい気持ちになりました。 今度は友人と一緒に「厄割石」の体験と「獅子頭守」の購入をしに行きたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉の二階堂にある神社です。鎌倉駅から歩いて20分くらいのところにあります。 金沢街道(県道204号)沿いの、岐れ道バス停のすぐ先から左側の脇道に入っていきます。 ところどころに行先表示があるので、分かりやすかったです。 入口に着くと鳥居の前に×字に交差した二本の木があり、その下をくぐるのがとても不思議な感じを受けました。 鳥居をくぐると参道の先に境内へと続く階段が見えました。 階段の下まで来ると看板があったので読んでみると、平安時代中期からの歴史があり、大宰府天満宮、北野天満宮と並び、日本三天神の一つに数えられているそうです。 階段を上り、門をくぐると真っ赤な拝殿が目の前に見えました。周りの建物は落ち着いた色合いなのでとてもきれいでした。 また、境内には漫画家ゆかりの筆塚があり、天神様とのつながりを感じました。 手水舎の奥に大きな木があったので少々気になっていましたが、調べてみると樹齢約900年の大銀杏の木のようで、掲載されていた紅葉の写真がとてもきれいだったので、見に行きたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 小町大路沿いに境内を構える日蓮宗の寺院、本覚寺を参詣しました。 源頼朝が御所の鬼門の守護のために建立した夷堂があった場所に建てられた寺院ということで知られる本覚寺。夷堂は今の山門前にあったと伝わります。今は境内に昭和56年に再建された夷堂を見ることができます。 仁王門をくぐり境内に入ると右側に夷堂、正面に本堂があります。本堂を右側に進むと日蓮の分骨を祀る日蓮御分骨堂を見ることができました。 そのほか、応永17年(1410年)の銘が入った梵鐘が吊るされた鐘楼や鎌倉時代末期から南北朝時代初期に活動した刀工、岡崎五郎正宗のものと伝わる墓所がありました。 朝のうちに訪れたので境内はとても静かでゆっくりと参詣することができました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉の二階堂にあるお寺です。鎌倉駅から歩いて25分くらいのところにあります。直ぐ近くに「杉本観音」というバス停があるので、そちらを利用されても良いかと思います。 入口のところにあった看板を読むと、奈良時代に出来た鎌倉最古のお寺と書いてあり、とても歴史のあるお寺のようです。 階段を登って行くと、両側に朱色の仁王様が立っている茅葺屋根の門があります。お札がたくさん貼られているのを見ると、地域の人に親しまれているのを感じました。 温暖化や近年の暴風雨で茅葺屋根の傷みが早いための、ご支援のお願いが書かれた看板があり、このようなところにも影響していることに少々驚きました。 門をくぐると正面に本堂へ続く階段が現れてきます。 階段はコケに覆われていてとてもきれいでしたが通ることが出来なくなっていました。通れなくて残念な気もしましたが、この雰囲気を壊したくない思いもあったので通行禁止なのには納得しました。 正面階段左側の階段を登って行くと本堂が見えてきます。茅葺屋根の本堂はとても存在感があり感動しました。 本堂は中にも入れるので、訪れた際は是非見学してみてください。 境内はとてもきれいに手入れがされており、清々しい雰囲気を感じました。 現在も復興が続けられており、山門も再建予定とのことなので、また訪れてみたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 江ノ島電鉄の極楽寺駅と鎌倉の大仏様で有名な高徳院がある長谷駅の間に神社があります。長谷駅から長谷寺に向かって歩いて途中を住宅街の中に入ります。ひたすら住宅街を歩いていくと神社の裏手の鳥居が見えて来ます。他には、長谷駅から極楽寺駅に戻る感じて線路に近い道をいくと正面の鳥居が見えて来ます。江ノ島電鉄の線路の側にあるので電車の中からも、神社が見えます。 読み方は「ごりょうじんじや」と読みます。私は「みたま」と読むと思ってました笑笑。そして、「権五郎神社」とも呼ばれるそうで、鎌倉七福神のひとつに数えられています。そういえば、七福神のお参りする社がありました笑笑。通りすがって参拝せず帰って来てしまいましたが、皆さんは是非お参りしてください。 梅雨時は、紫陽花が咲いていてとても風情があります。本殿の社の隣には海を守る神様が祀られていて、鎌倉に住む人たちの守り神として地域に密着していたんだなと思いました。鳥居から中に入ると、住宅街の中にあり観光客で賑わう通りから外れているせいか、雨が降っていれば、静かで雨音しか聞こえてこない感じです。そしてなぜか、空気が冷たく感じます。物足りないと感じるかもしれませんが、1人でぼーっとしたい人はおすすめです。曇っている時にお出かけの際は、羽織るものを持って行った方がいいです。 因みに、御朱印はちゃんと手書きで書いてくれます。猫のスタンプが押してあるのが可愛くてとてもお気に入りです。 もしかしたら天気のいい日には、猫ちゃんに会えるのかもしれません。 今度お参りに行った時は、猫ちゃんのスタンプの理由を聞いてみようと思います。 わかる人は是非ホームメイトリサーチに投稿して下さい。 私も次に行った時は猫ちゃんがいるか見に行きたいと思います。 おみくじも昔ながらの普通のおみくじで、200円でくじを引く事ができます。普通のくじと、恋みくじの2種類あるので、デートの時は恋みくじを引くのもいいと思います。 そして、お参りする時は早めに行かないと御朱印をもらう事ができなくなるかもしれませんので、インターネットで確認して下さい。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉駅から徒歩10分くらいのところにあるお寺です。 鶴岡八幡宮を右に曲がって少し進んだ突き当りにあります。 参道に入って直ぐのところにある看板を読んでみると、新田義貞の鎌倉攻めで滅亡した北条氏の霊を弔うために後醍醐天皇が足利尊氏に命じて建てられたようです。 更に参道を進むと本堂前の開けた境内に着きます。 とてもきれいに手入れがされており、清々しい気持ちになりました。 また、本堂の横にある大きなイブキの木がとても印象に残りました。 参道の両側には御堂や慰霊碑が幾つか建っており、一番奥の御堂が大聖天のものだったので、入口にあった「大聖天」の大きな石碑に納得しました。 本堂の中には沢山の仏像が祀られており、厳粛な雰囲気だったので緊張してしまいました。 後で調べて分かったのですが、「萩寺」という名前でも親しまれているようなので、秋のお彼岸時期にまた訪れてみたいと思います。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 成就院は、弘法大師が修行された護摩壇跡に第3代執権の北条泰時が京都から辰斎上人を招いて、1219年建立しました。 鎌倉エリアでアジサイ寺として有名でしたが、2019年の創建800年に向けての参道工事にて一面のアジナイではなくなっています。 以前参道には「般若心経」の文字数と同じ262株のアジサイがありましたが、30株ぐらいまでに減ったそうです。 参道のアジサイは東北へのご縁が広がることを願って、宮城県 南三陸町へ送り、現在はアジサイの代わりに宮城県県花のハギを植えているそうです。 一面のアジサイはもう見られませんが、今後はハギを楽しみにしたいです。 山門前から見える弧を描いて広がる由比ヶ浜、材木座海岸の一望は健在で、鎌倉でも屈指の絶景ポイントになっています。 コロナ禍でお守りやご朱印などセルフ対応でした。 前回はコロナなど知らない頃の暑い日の参拝だったため、暑さに気をつけての心づかいと塩味せんべいをくださったこと、懐かしく思いました。 平穏な日々に戻ることを祈るばかりです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 鎌倉にある雪の下教会は、私が子供の頃からずっとあるカトリックの教会です。段葛に面している若宮大路の道にあります。 大正6年1917年に伝道が始まり、昭和16年1941年に鎌倉カトリック雪の下教会になったそうです。思っていたより歴史のある教会でした。昔、妹がこの教会で活動する合唱団に所属していましたので、よくこの教会で合唱を聴きました。定期的にバザーなども開催しています。 この教会は、とても大きな教会で、中はすっきりしていてとても美しい建築です。光の入り具合も神秘的で、厳かな気持ちになります。 なんとパイプオルガンもあります。演奏している時に遭遇できればラッキーです。とてもいい音色のオルガンです。 教会正面の上部には聖母マリアのモザイク画があります。素敵な教会であることを感じます。 そして、この教会では結婚式を挙げることもできます。結婚の講座を受けることや、司祭と面談する必要がありますが、とても厳かな結婚式になりそうですね。日曜日以外で実施できるようです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 浄妙寺(じょうみょうじ)は、鎌倉市にある臨済宗建長寺派の古寺で、文治4年(1188年)に源頼朝の家臣であった足利義兼によって創建されました。当初は密教の寺院として極楽寺と呼ばれていましたが、建長寺を開山した蘭渓道隆の弟子である月峯了然が住職となり、禅宗の寺院に改められました。 浄妙寺は鎌倉五山の第五位に位置し、かつては七堂伽藍や塔頭二十三院を有する大規模な寺院でしたが、火災などにより多くの建物が失われました。現在でも本堂や客殿、喜泉庵などが残っており、特に喜泉庵の枯山水庭園は美しい景観を楽しむことができます。 文化的には、浄妙寺は婦人病や子宝にご利益があるとされる淡島明神像を安置しており、多くの参拝者が訪れます。また、境内には足利貞氏の墓とされる宝篋印塔があり、歴史的な価値も高いです。 浄妙寺は四季折々の花々が美しく、春にはボタン、秋には紅葉、冬にはウメが境内を彩ります。さらに、毎年10月には草花に感謝の意を込める「花供養」が行われます。浄妙寺の境内にある茶室「喜泉庵(きせんあん)」で抹茶を楽しむことができます。喜泉庵は枯山水の庭園を眺めながら、落ち着いた雰囲気の中で抹茶をいただける場所です。 メニュー 抹茶と生菓子:1,100円(税込) 抹茶と干菓子:660円(税込) 生菓子は季節ごとに変わり、美しい和菓子が提供されます。干菓子はシンプルな甘さの落雁などが楽しめます。 拝観料/入館料 大人(中学生以上):100円 小学生:50円 障害者:無料(要障害者手帳) 市内高齢者:無料(要福寿手帳) 営業時間 夏季:10:00〜16:30 冬季:10:00〜16:00 アクセス 浄妙寺はJR鎌倉駅から京急バスで約12分、「浄明寺」バス停で下車し、徒歩約4分の場所にあります。 また、浄妙寺には「石窯ガーデンテラス」というレストランもあり、自家製パンやコーヒーを楽しむことができます。 浄妙寺での抹茶体験は、静かな環境で心を落ち着けるのに最適です。ぜひ訪れてみてくださいね!
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本