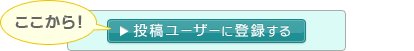こちらの氷川鍬神社(ひかわくわじんじゃ)は、JR上尾駅東口から約200メートル程の距離にあり、旧中仙道を大宮方面に歩いて行くと右側にある神社です。 こちらの神社は、江戸時代初期の万治のころに(1658〜61年)創建されたと言われており(一説では寛永9年の1632年とも)、明治末期の神社の合祀(ごうし)以後の社名との事で、合祀以前の社名は、御鍬太神宮(おくわだいじんぐう)と呼ばれていたそうです。 そうした経緯より地元では「お鍬さま」と呼び親しまれているそうです。伝承によると、3人の童子が鍬2挺と稲束を持ち、白幣(はくへい)をかざし踊り歩いて上尾宿にやって来て、童子たちはいずこにか消え失せたが、残された鍬を本陣の林宮内(くない)が祭ったのが社名に鍬がつく馴れ初めのなんだとか… 境内には本殿の他に、学業の神様である菅原道真公や朱子を奉った二賢堂、雲室上人生祠碑頌や聖徳太子堂、浅間社などもあるそうです。